大学祭パンフレット等に記載されているテーマの設定理由や、大学祭のねらいをかみ砕いてまとめました。記載のない箇所はパンフレットを見つけられていない回ですので、お持ちの方はご連絡いただけると幸いです。このページの一部は、広島大学文書研究会(現:なんでも総研)OBのNさんの資料をもとに作成しています。
第1回~第10回(1952年~1961年)
第11回~第20回(1962年~1971年)
戦後からの民主主義観が変容していく事について危惧を抱いた。
大学祭において、ヒロシマで学ぶ学生として戦後20年の現代に対して思うところを精一杯発信する事を目指した。
大学祭では、戦後世代の自分達が社会に対して行動を起こすための思想の原点を探すべきだと考えた。
日常に埋没していく事(=癒着)で、薄れゆく反戦反核の意識を問いただすべきではないかと考えた。
「常識」という権力者に奪われている日常を自分たちで突破して、自分達のもの(=砦)とする事を目指した。
広大の現状と未来を探り、未来への展望としての第18回大学祭を「広大創造祭」として、新しいイメージの大学祭を創り上げる事を目指した。
第17回テーマの発展。権力者によって操られている日常を、常に標的を狙うがごとく批判的に過ごすべきであるとの意見を込めた。
第21回~第30回(1972年~1981年)
いずれ大学を去る自分達であるが、統合移転を巡って、現実に目を向け、何らかのかかわりを持ち、そこからさらに進んだ大学像を創り上げていくべきだと考えた。
大学祭実行委員会のクラス会制度実施を契機に、これまでくすぶっていた実委への不満が爆発。テーマの決定やパンフレットの発行ができない事態に。
キャンパスを埋め尽くす自分達は如何にあるべきかを問いかけた。
体制側の操り人形のように受動的に行動するのではなく、主体的に社会を考え・行動する機会の一つとして大学祭を位置づけ、主体的参加を呼び掛けた。
自らの事のみを考え、社会の様々な問題に対して無知(=不知鳥)になるのではなく、大学生だからこそ、これから志す学問を通じて社会・人間を考えるべきと主張した。
大学生である自分達の存在が体制側の座標軸(思惑・計算)上におかれる事を憂い、自分たちの存在行動を規定する座標軸を奪い返すために自主的な大学祭の実施を訴えた。
常識という戒厳令の下で現状に甘んじ、沈黙を続けるのではなく、声に出して行動に移すべきであると主張した。
第31回~第40回(1982年~1991年)
権力者の「うそ」のままに、「検定」が許すままに行動していくと、いずれ「今度はあんたの当番じゃん」と侵略戦争に導かれていく事になると訴え、うそを指摘する勇気を持つべきであるとした。
学生の価値観の多様化。今後どのような大学祭を作っていくべきか、暗中模索である。
大学祭が「年中行事」と化し、開催自体は危ぶまれなくなった。ただ内容はどうか。バザー・ステージ企画は増えていく。一般企画は減っていく…。
大学祭の今後の方針、西条移転後の展望が見えない。どこにあるんだろうか。
大学祭の成功とは何か。人が集まること?有名人のコンサートを開けば人は集まるだろうが、それが本当の大学祭と言えるだろうか。確かに、当日は満足感が得られるだろうが、それは他者から与えられた満足感であって、自分の行動に対する満足感ではない。「ゲーノー人が来るだけが大学祭じゃねえぞ」
「マンネリ」は悪いことか?企画者自身が価値を見出しているならそれで良い。それを判断するのもまた、企画者以外にはできない。
マンネリ化が叫ばれる学祭、西条ではそのマンネリと化した大学祭すらできるか不安である(大学の規制、学外からの来訪者減、休講措置の廃止など)。権利の上に惰眠を貪っていたのでは、いつこの中(束縛・分断・統制)に捕まってしまうのか知れたものではない。
バンドと模擬店ばかりの大学祭…。
マンネリ化、偏った企画。これが学祭が面白くない原因。もっと個性を活かしてほしい。
大学祭参加団体の多くがバザーへと企画を変え、普通の企画が減りつつある。
政治色の強かった時代、流行を追い求める時代から「個性的」が叫ばれる時代へ。だが我々は「個性的」だろうか?大学祭も同じ。マンネリ化。大学にとって大きな節目、私たちもキバリ直す時期だ。前例慣例お構いなし、やりたいことができる大学祭。これを放っておく手はない。最後に一花咲かせてやろう。
第41回~第50回(1992年~2001年)
「見ざる、聞かざる、言わざる」のアンチテーゼとして設定し、大学祭を「対象の本質を見、聞き、自分の意見を言う」きっかけとしようと呼びかけた。さらに大学祭を見て、聞いて、自分たちも参加して、自分の想いを言ってほしいという希望を込めた。
全学を挙げての西条での大学祭は今回が初めて。広島市内と大きく環境が異なる西条に来た今こそ、積極的に自分を磨くことの重要性に気づき、行動すべきだと呼びかけた。
準備中…
準備中…
準備中…
前日が雨でも祭の準備はする。明日晴れた後、祭ができることを信じて。「晴れ」てほしいという実委の思い。
一昨年までの実委の役割は祭を行う「うつわ」作り、去年はマンネリ化した大学祭の打破、そして今年は祭を主催する大学生が純粋に楽しめる祭を。
(準備中…)
第51回~第60回(2002年~2011年)
準備中…
小さいころ感じた物語へあこがれやときめきを思い出し、祭を楽しんでもらえるように「世界の物語」「日本の物語」をテーマに開催。この年から前夜祭を開始。(HU-styleより)
祭独特の雰囲気を大学祭で満喫してほしい。「トマト祭」「牛追祭」「鬼祭」と、1日ごとに祭のテーマを設定。
どの大学祭にも負けない、最高にして最大の祭にしたいという願いを込めた。(HU-styleより)
広島大学のキャンパスを「色」でゾーン分けし、ゾーンごとに様々な企画を用意した。
2009年は広島大学創立60周年であり、60年分の感謝の気持ちを込めた「愛」をテーマにしている。(HU-styleより)
来場者に楽しんでもらおうという思いを込めた。
来場者に笑顔になってもらえる大学祭をつくろう、そこで生まれた笑顔のパワーを東日本大震災の復興に尽力されている方へ届けていこうという思いを込めた。
第61回~第70回(2012年~2021年)
率直な思いを込めた。様々な企画を通し、来場者が楽しめるような祭にしたい。
あらゆる色を選んでとりあわせる「彩(いろどり)」のように、大学祭の会場で来場者自身の手で会場にあふれる色・思い出をとりあわせてもらいたい。
果実は昔から人間の生活に欠かせないものであり、多くの形、色、美しさを持っている。それは日本人にとっての祭と同じである。この大学祭も、広大生にとっての果実のような存在でありたい。
第71回~(2022年~)
夏に開催予定だったゆかたまつりが悪天候により中止に。その悔しさを踏まえ、生まれ変わってリベンジ・再挑戦したいという思いを込めた。
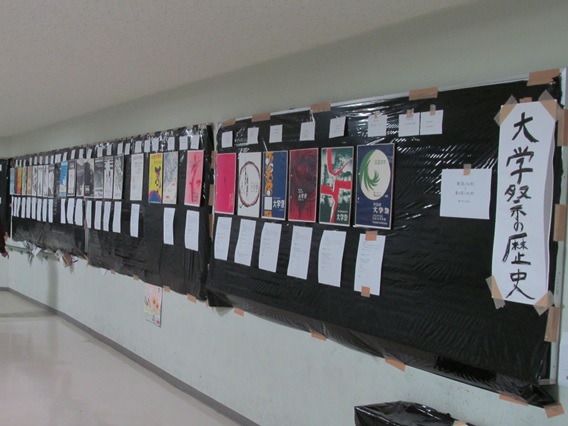
コメント